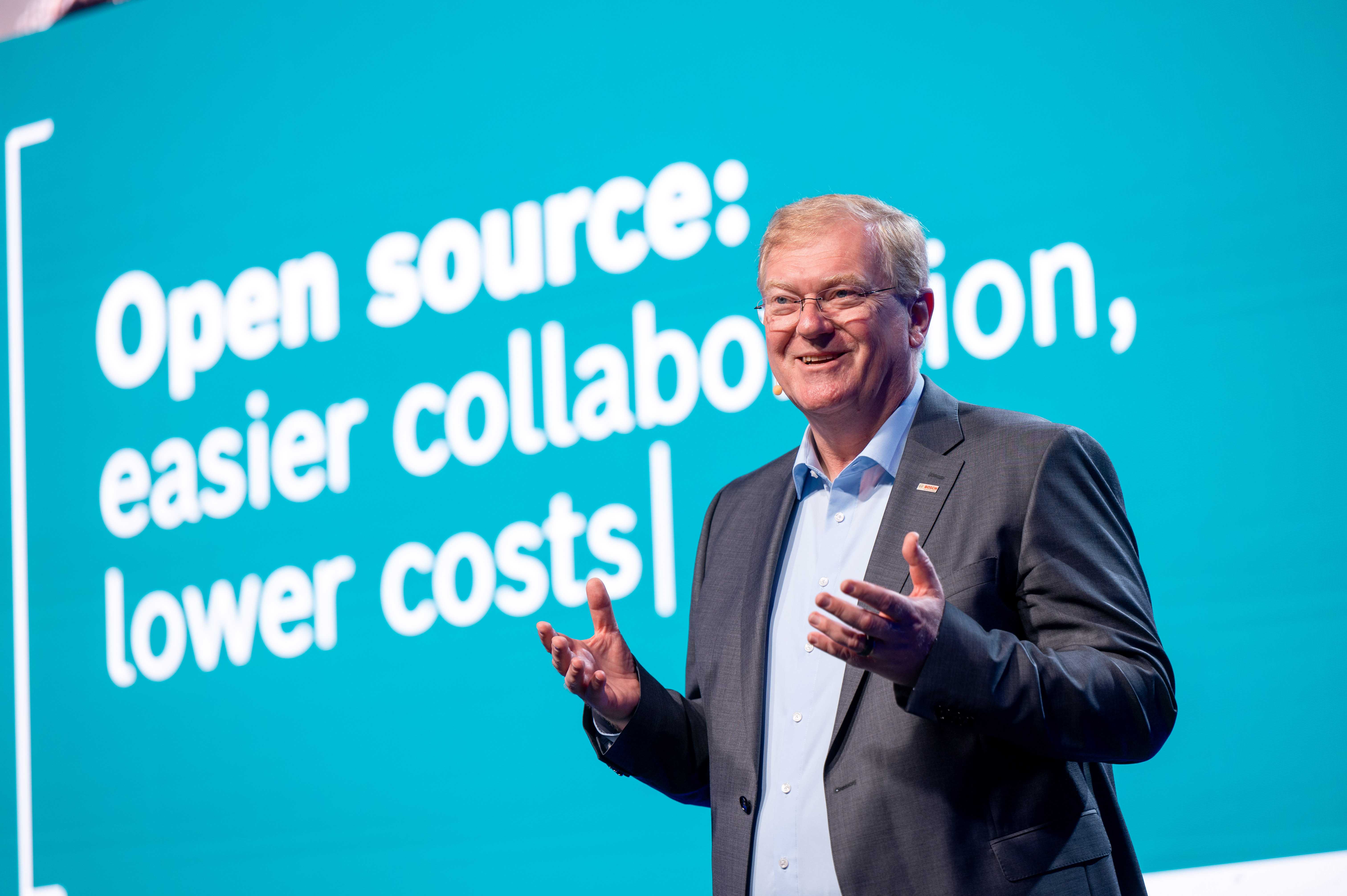レニンゲン(ドイツ) – ボッシュにおいて最も重要となるのは、プログラミングです。グローバル規模で革新的なテクノロジーとサービスを提供するボッシュは、ソフトウェアとサービスによって事業を拡大しています。2030年までに、ボッシュはソフトウェアによって数十億ユーロ規模の売上高の達成を目指しています。ロバート・ボッシュGmbH取締役会会長のシュテファン・ハルトゥングは、レニンゲンで開催されたBosch Tech Day 2024で次のように述べました。「かなり前から、ボッシュはソフトウェア企業でもありました。当社全体における幅広い分野の専門知識を活かし、ソフトウェアを直接製品に組み込むことが可能です。私たちの製品に使われているソフトウェアには、人々の生活を向上する『Invented for life』なテクノロジーが駆使されています」
ロバート・ボッシュGmbH取締役会会長のシュテファン・ハルトゥング
ボッシュのソフトウェアは、すでに大手産業企業の生産ラインや多くの車両修理工場、医療機器など、多方面で使用されています。ドライバーに逆走車について警告する逆走警報システム、貴重な資産の保護、商業ビル向け技術、さらには宇宙空間や国際宇宙ステーションでも活躍しています。ボッシュでは合計48,000人の従業員がソフトウェアのプログラミングに携わっており、そのうち42,000人がモビリティ事業セクターに属しています。ハルトゥングは、「ソフトウェアは、自動車業界を抜本的に変革するでしょう」と述べました。さらに、ロバート・ボッシュGmbH取締役会メンバー兼モビリティ事業セクター会長のマルクス・ハインも、次のように語ります。「将来的には、車両はデジタルの世界にシームレスに統合されることでしょう。その結果、何よりも車両がアップデート可能なものとなるのです」。そうすれば、修理工場を訪れることなく、ソフトウェアの便利なOTA(Over-the-Air)アップデートにより、新機能を入手できるようになります。マルクス・ハインの言葉を使うなら、「ボッシュのテクノロジーにより、車両の経年劣化を遅らせることが出来るようになります」。乗用車だけでなく、トラック、二輪車、eBikeにも、アップデートによって新しい安全機能や便利な機能が追加されるようになります。2021年末に「eBike Flowアプリ」を発表して以来、ボッシュはこのeBike向けのスマートシステムを通じて、警告音、トラッキング機能、新しい走行モードなど、約70の新機能や改良を導入してきました。
ロバート・ボッシュGmbH取締役会メンバー兼モビリティ事業セクター会長のマルクス・ハイン
企業の垣根を越えてソフトウェアに秘められた可能性を引き出す
現在、ボッシュにおける事業の成功の柱となっているのはソフトウェアとデジタルサービスであり、これらは企業や産業の垣根を越えたイノベーションの原動力・実現要因となっています。モビリティ、製造、ビルディングテクノロジーなどの幅広い分野における知識と専門技術を有するボッシュは、従来IT分野をリードしてきた企業において人気の高いパートナーとなっています。ハルトゥングは、次のように語ります。「ソフトウェアとAIに秘められた大きな可能性を活用するには、対等なパートナーシップが必要です。これを自社だけで管理できる企業はほとんどありません。このような状況において、企業の垣根を越えて専門知識を共有し、コストを削減し、標準化されたソリューションを生み出すために特に有益な方法となるのが、オープンソースソフトウェアです」
政策立案者も重要な役割を担います。ソフトウェア開発ではAIがますます重要になっていますが、AIに関して企業に必要なのは計画の確実性です。これは、欧州連合で最近可決されたAI法にも当てはまります。ハルトゥングは、「EUでは現在、AI法に基づく規格を迅速に策定する必要性が生じています。規制は必要ですが、テクノロジーの進化の歩みを不必要に鈍化させたり、変革を妨げたりしてはならないからです」と述べています。
ソフトウェア・デファインド・モビリティの時代の幕開け
自動車業界の新しいトレンドは、「ソフトウェア・ディファインド・ビークル」と称されています。ソフトウェアは、新しい車両モデルの設計と開発の出発点として、ますます脚光を浴びています。最近のマッキンゼーの調査報告書では、自動車用ソフトウェアとエレクトロニクスの世界市場は、2030年までに4,620億ドルに達すると予測されています。2023年以降、車両に占めるソフトウェアの割合は3倍になる見込みです。ボッシュはこの成長市場に加わり、世界中の自動車メーカーにとって信頼性の高いパートナーであり続けたいと考えています。「ソフトウェア・ディファインド・ビークルの時代が幕を開けようとしています」とハインは述べ、こう続けました。「ボッシュにとって、このトレンドは追い風となります。なぜなら、ボッシュはハードウェアとソフトウェアの両方に精通しているからです。私たちは自動車エレクトロニクスとクラウドの相互作用に完全に精通する、数少ない企業のひとつなのです」。たとえば、Vehicle Healthのようなソフトウェアとサービスソリューションの提供により、ボッシュはフリート運用者における車両の故障回避、ならびに効率向上を支援します。また、物流会社に対しては、デジタルプラットフォームのBosch L.OSによりデジタル化を促進し、オペレーションチェーン全体を簡素化しています。さらにボッシュは、プロのドライバーが運転するかのように、ほとんど揺れのない非常にスムーズな停止を可能とする特別なソフトウェアを開発しました。このボッシュの「eBrake to Zero」機能により、停止と発進を繰り返す運転時のブレーキ操作が快適でリラックスできるものになるだけでなく、同乗者の乗り物酔いの防止にも繋がります。「プロのドライバーと同じくらいスムーズにブレーキをかけるソフトウェアにより、揺れのない停止と発進を実現します」と、ハインは語りました。
ソフトウェア・ディファインド・モビリティは、車両アーキテクチャの変化とも密接に関係しています。従来のドメイン固有ITとエレクトロニクスアーキテクチャから、少数の非常に強力なコンピューターとセンサーを用いた集中化されたクロスドメインのアーキテクチャに移行しつつあるのです。現在、1台の車両には、複数メーカーのコントロールユニットが約100台搭載されています。将来のソフトウェア・ディファインド・ビークルでは、十数台の車両コンピューターによって機能が制御されるようになるでしょう。これを実現するには、最新の車両コンピューターにドメイン固有機能を組み合わせる必要があります。こうした状況を踏まえ、今年初めにボッシュとQualcommは共同で新しい車両コンピューターを発表しました。このコンピューターにおいて、インフォテインメントと運転支援機能が初めて統合されました。これは、自動車メーカーにとっては設置スペース、ケーブル数、重量の削減のみならず、さらに重要なことに、コスト削減にもつながります。インフォテインメントと運転支援の統合により、コントロールユニットだけでも最大30%のコスト削減が可能になります。高度な車両コンピューター全般において、すでにボッシュは成功への道を歩みつつあります。こうしたコンピューターにより、過去3年間でボッシュは40億ユーロ近い売上高を達成しました。
しかし、100台であろうと十数台であろうと、車両の多様なコンピューターとソフトウェアパッケージは、ブランドの垣根を越えて通信できるように、相互にネットワーク化する必要があります。ボッシュの子会社イータス(ETAS GmbH)は、このためのミドルウェア(車両の物理的なコンポーネントとアプリケーション ソフトウェア間の変換ソフトウェア)を提供しています。これにより、異なるサプライヤー製のものでも連動が可能になります。現在、ボッシュの部品を搭載していない車両がほとんどないように、将来的にはあらゆる車両にボッシュのソフトウェアが搭載されるでしょう。